- HOME>
- Komoda Law Office News

2024.06.21 Komoda Law Office News労働問題
1ヵ月単位の変形労働時間制の適用について~弁護士が回答!Q&A~
Question. 当社は1ヵ月単位の変形労働時間制を導入しており,スタッフはシフトで決まった時間に勤務してい...

2024.06.13 Komoda Law Office News中山弁護士動画解説ブログ
NDAは秘密保持契約とも言いますが、取引をするにあたって自社の機密情報を相手方に開示をするときの機密情報の取り...

2024.05.02 Komoda Law Office News時事問題
2024年(令和6年)3月22日、福岡県性暴力根絶条例(正式には、「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県...

2024.03.15 Komoda Law Office News川本弁護士の動画解説ブログ
元検事・元司法試験考査委員(憲法)が考える司法試験―司法試験(憲法)で問われているものは何か?
これから法曹を目指される方に向けて、元検事・憲法の司法試験考査委員も務めた弁護士が考える司法試験というテーマの...
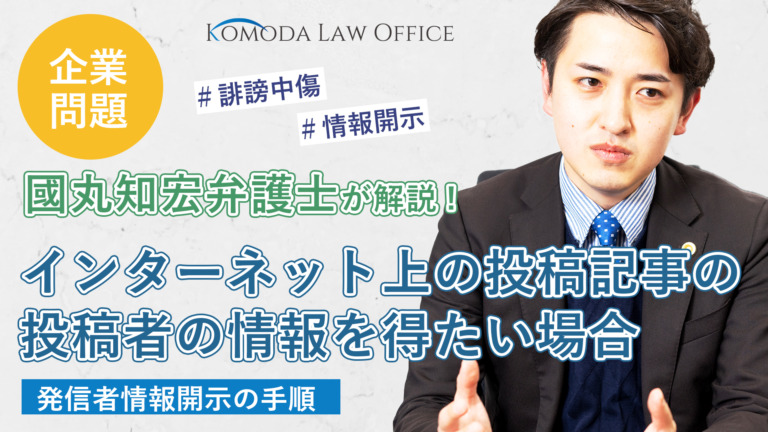
2024.03.14 國丸弁護士の動画解説ブログ
インターネット上の投稿記事の投稿者の情報を得たい場合に取り得る手順
前回は、インターネット上で自社に関する誹謗中傷や名誉棄損に当たる投稿記事が出回っている場合の削除方法について説...













