- HOME>
- Komoda Law Office News>
- 企業関連

2023.10.06 Komoda Law Office News企業関連
イグジットを目指すベンチャー企業が注意すべき点は?ベンチャー企業の株式の保有割合や資本政策の留意点を弁護士が解説
Question. 知人と一緒にベンチャー企業を立ち上げて、最終的にはイグジットしたいと考えていますが、株式の...

2023.07.18 Komoda Law Office News企業関連
【2022年1月改正】電子帳簿保存法と改正の内容について~②
今回は前回に引き続き、電子帳簿保存法の内容について、お話ししたいと思います。 前回の記事はこちらから:【202...
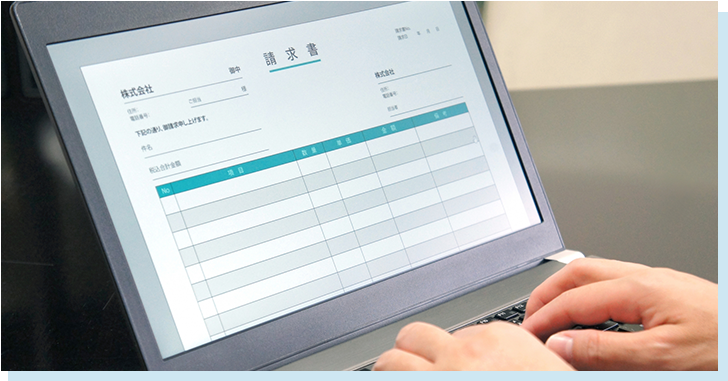
2023.07.12 Komoda Law Office News企業関連
【2022年1月改正】電子帳簿保存法と改正の内容について~①
各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するための電子帳簿保存法という法律をご存知でしょう...

2022.03.14 Komoda Law Office News企業関連
はじめに ICT(情報通信技術)を用いるなどして、商品の販売や事業活動の促進等に寄与するビジネスモデル(ビジネ...

2021.10.26 Komoda Law Office News企業関連
最近、ニュースなどでパワーハラスメント(略してパワハラ)という言葉をよく耳にするようになりました。 パワハラの...













