- HOME>
- Komoda Law Office News>
- 不動産関連
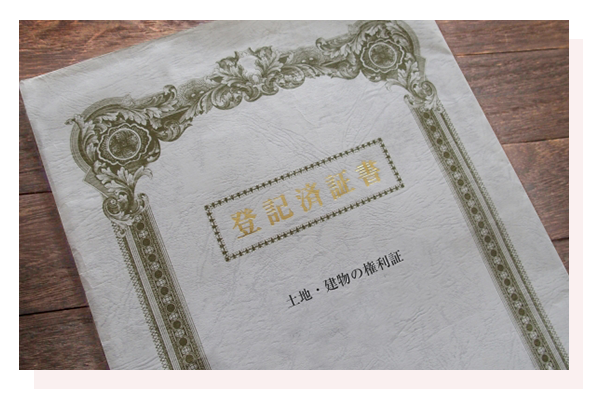
2024.01.19 Komoda Law Office News不動産関連
不動産の売買や相続をしたときは、その権利変動を登記によって公示することとされていますが、所有者が次々と変わった...

2023.12.13 Komoda Law Office News不動産関連
1.告知義務・重要事項説明義務 宅地建物取引業法47条1項1号は、同法35条1項各号又は2項各号に規定する重要...

2023.12.01 Komoda Law Office News不動産関連
【最決令和5年10月6日】1筆の土地の一部についての登記請求権を保全するために当該土地全部について処分禁止の仮処分命令を申し立てることの可否
1筆の土地の一部についての登記請求権を保全するために当該土地全部について処分禁止の仮処分命令を申し立てることの...

2022.01.17 Komoda Law Office News不動産関連
問題事例 1 私は、賃貸物件の経営に乗り出そうと考え、手ごろな収益物件を探していたところ、とある賃貸物件1...

2021.12.01 Komoda Law Office News不動産関連
皆さんが勤めている会社から支給される賃金に、「住宅手当」、「家族手当」といった項目の手当があるかと思います。 ...













