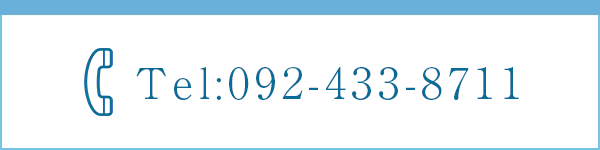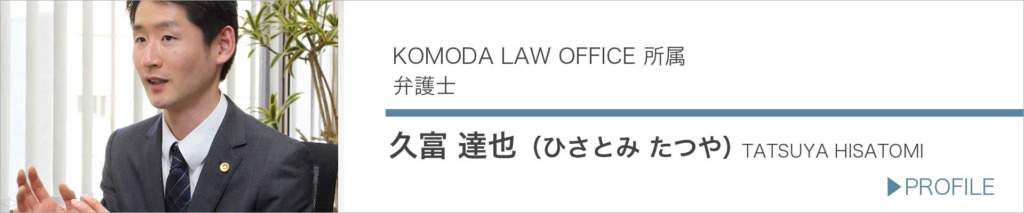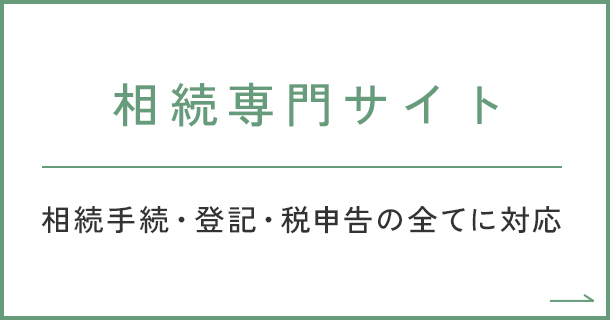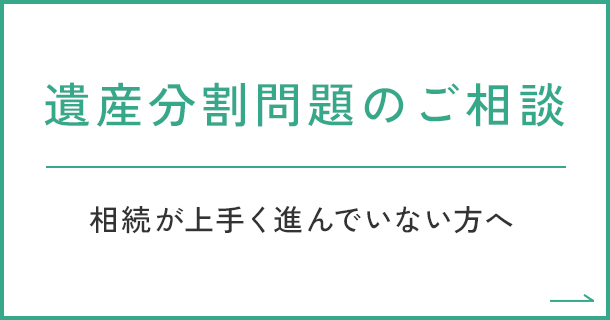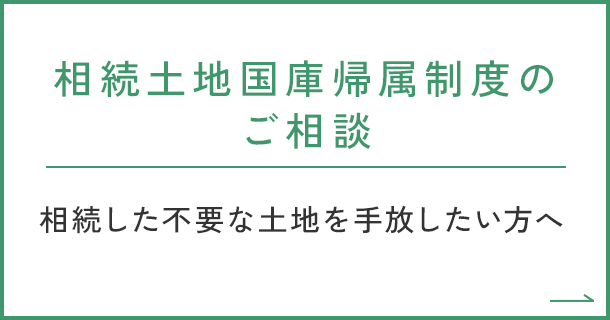不動産の売買や相続をしたときは、その権利変動を登記によって公示することとされていますが、所有者が次々と変わったような場合には、手続の煩雑化や登録免許税の負担を嫌って、中間者の一部を除いて登記を済ませてしまうことができないか、との要請が生まれました。
今回は、いわゆる「中間省略登記」について、議論の過程と現行法に則った解釈、及び実行方法の一部を概観します。
1.登記制度の建前
不動産に関する権利の取得、喪失、変更があったときは、当事者が登記所(法務局)に申請して登記がなされることによって、それらの権利変動を公示することとされています。
現行の不動産登記制度は、権利の変動過程を忠実に登記記録に反映させることを目的としており、登記申請に際しては、売買、相続をはじめとする契約や事実関係を証明する情報(登記原因証明情報)の添付を必須とし、実体に沿わない架空の登記がなされることを防止しているわけです。
ところが、不動産の譲渡が繰り返され、次々と所有者が変わるような場面では、逐一登記を行う手間や登録免許税の負担を省略したいとの要請が生まれます。
そこで、実際にはA→B→Cへの譲渡がなされたのに対し、登記はA→Cのみで済ませることができないか、様々な便法が考え出されていますが、平成16年の不動産登記法全面改正以降、中間省略登記は困難となったと言われることがあります。
2.旧法下と新法下の状況の違い
(1)平成16年改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)の下では、昭和初期~中期の判例を根拠に、「中間者の同意があれば中間省略登記は可能」などと言われることがありました。
確かに、戦前の大審院判例の中には中間省略登記請求を認めたとされるものが存在しますしし、戦後においても、いったんなされてしまった中間省略登記の抹消登記手続請求を否定した判例(最判昭和35年4月21日民集14巻6号946頁)や、中間省略登記の請求を棄却した理由中の傍論で「登記名義人及び中間者の同意があれば別」などと述べた判例(最判昭和40年9月21日民集19巻6号1560頁)が見られます。
しかし、裁判所の判断対象となるのは、あくまで最終的な不動産取得者等が、取引相手方や登記名義人等に対する「登記請求権」=登記手続をするとの意思表示を求める権利があるかどうかについてであって、登記所に対する「登記申請権」の有無についてではないことに注意しなければならないです。
すなわち、「判決による登記」の制度があることで、登記手続を命じる判決があれば、申請者は単独で登記申請が可能で、登記所は判決どおりの登記をする他ないことから、その結果として中間省略となるような登記がなされることはあり得ます。

他方、登記所はあくまで権利変動過程を忠実に反映した登記申請のみを受理するから、A→B→Cと不動産所有権が順次移転した場合において、中間者の同意書等を添付したからといって、A→Cへの登記申請が受理されることはありませんでした。
この点は、旧法下でも現行法下でも同様です。
(2)しかし、旧法下では、登記申請時に添付すべき登記原因証書に代えて、申請書副本を添付することでも足りることとされていたことから、形式的審査権しか有しない登記官は、申請書どおりの登記を受け付ける他なく、申請者がA→Cへの直接の権利変動があったかのように申請書類を作成して提出すれば、結果として、A→Cへの中間省略となるような登記がなされることがあり得ました。(なお、上記のような申請を行うことは、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に該当し得るとされます。)。
(3)これに対し、現行法下では、登記原因証明情報の添付が必須化され、その形式も厳格化されたことから、実際にはA→B→Cという権利変動があったのに、A→Cへと直接権利が移転したかのように装うことはほぼ不可能となりました。
このことが、実質的にも中間省略登記を行うことはできなくなったといわれるようになった所以です。
なお、近時の最高裁は、「不動産の所有権が、元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対し、元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし、許されないものというべきである。」(最判平成22年12月16日民集64巻8号2050頁)とし、中間者の同意の有無にかかわらず、中間省略となるような「登記請求権」をも認めない旨判断しています。
「真正な登記名義の回復」という登記原因は、真実と異なる登記がなされた後、これを前提に第三者の権利(抵当権)が設定されてしまい、当該権利者から抹消についての承諾が得られないような場合に、便宜的に所有権移転登記の形をもって真の権利者へと登記を移転させるような場合に用いられるものではありますが、最高裁は、現在の所有者Cがこの登記原因を便法として登記請求をし、「判決による登記」を図ることも否定したものといえます。
3.新中間省略登記
現行法を前提として、実質的に中間省略となるような登記を実現するにはどうすれば良いでしょうか。
そのためには、不登法があくまで権利変動の過程を忠実に登記記録に反映させることを目的としていることに着目し、実体的にもA→Cの権利変動があったと構成すれば良いことになります。
そのために考え出された方法としては、以下のようなものが挙げられるが、多用されているのは⑵のようです(これらを総称して「新中間省略登記」と呼ばれます。)。
(1)買主たる地位の譲渡方式
A→Bの売買契約締結後、Bが買主たる地位をCに譲渡する(Aはこれを承諾します)。
Bが得る転売差益がいくらか知られてしまうこと、Bが契約から離脱するため、代金額を売上として計上できないこと等の難点があることから、⑵ほど普及しなかった模様です。
(2)第三者のためにする契約方式
A→Bの第一契約の買主が、所有権の移転先となる者の指定権を与えられ、B→Cの第二契約(他人物の売買)締結後又は締結と同時にCが受益の意思表示をし、Bが上記指定権を行使してAを所有権移転先として指定し、A→Cへの直接の権利移転を構成します。
以下は第一契約における特約条項の一例です。
1(所有権の移転先及び移転時期)
買主は、本物件の所有権の移転先となる者(買主を含む。)を指定するものとし、売主は、買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件として、本物件の所有権を、買主の指定する者に対し直接移転することとします。
2(所有権留保)
売買代金全額を支払った後であっても、買主が改めて書面により、買主自身を本物件の所有権の移転先として指定しない限り、買主に本物件の所有権は移転しないものとします。
3(受益の意思表示の受領委託)
売主は、買主に対し、移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権の移転を受ける意思表示」の受領権限を与えます。
4(買主の移転債務の履行の引受け)
買主以外の者に本物件の所有権を移転させるときは、売主は、買主がその者に対して負う所有権の移転債務を履行するために、その者に本物件の所有権を直接移転するものとします。
なお、第一買主Bが宅建業者の場合、1項の「所有権の移転先となる者」として「(買主を含む。)」という文言を入れておくことを要します。
これは、宅建業法33条の2が、宅建業者が他人物である宅地又は建物を販売することを原則として禁じる一方、「宅建業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合」にのみ例外的に許容しているためです。
それゆえ、第一契約において、「所有権の移転先となる者」として「(買主を含む。)」という文言を規定することによって、上記の例外に該当することとして、B→C間の第二契約が同条違反となることを防止し得ます。
宅建業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでないです。
一宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
(3)まとめ
前記の方法により、実際にA→Cへの直接の権利移転があった形で契約をすることで、その変動過程に沿ったものとして、実質的に中間省略登記を実現することは可能です。
ただし、中間省略のメリットを享受し得る一方で、Cは、Bに対してはともかく、Aに契約不適合責任の追及はできないなど、万全の方法ではないことには注意が必要です。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。