- HOME>
- Komoda Law Office News>
- 労働問題

2022.01.31 Komoda Law Office News労働問題
はじめに 皆さんは「管理監督者」という言葉をご存知でしょうか。 「管理」という響きから「管理監督者」=「管理職...
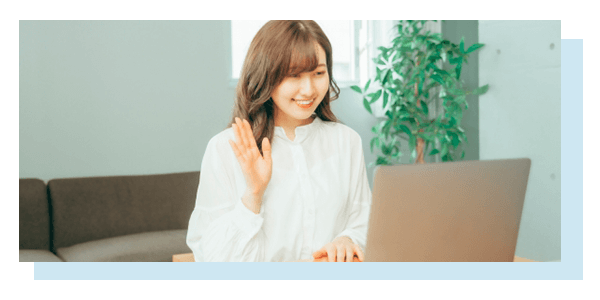
2022.01.05 Komoda Law Office News労働問題
2020年、新型コロナウイルス感染症の世界的感染爆発に伴い、日本でも緊急事態宣言が発令され、企業においてテレワ...
2019.08.26 Komoda Law Office News労働問題
今回の記事では、経理の定例業務についてお話します。経理は、税金や会計に関する業務全般に携わります。そのため,迅...
2019.08.25 Komoda Law Office News労働問題
今回の記事では、人事の定例業務についてお話します。人事は、入社・退社などの従業員に関する手続き全般に携わります...
2019.08.24 Komoda Law Office News労働問題
皆さんは会社の「事務」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?偏に事務といっても、総務、人事、経理など様々な業...













